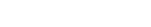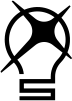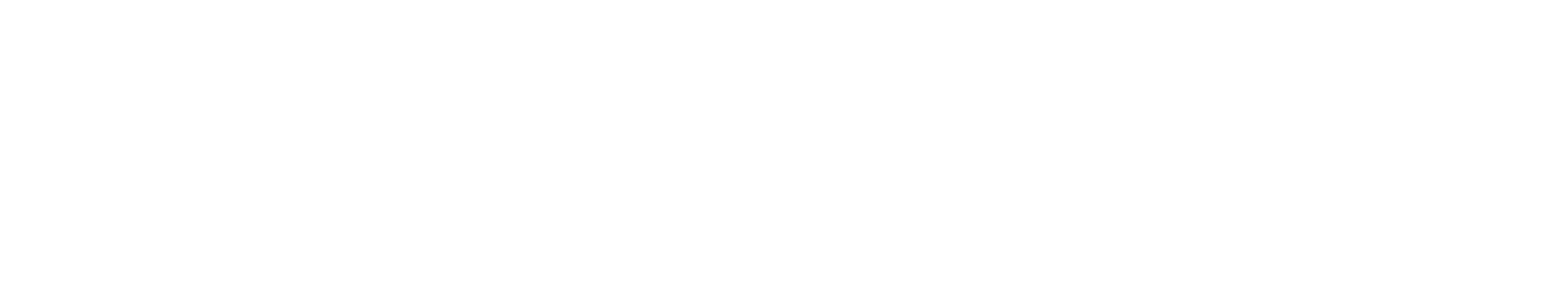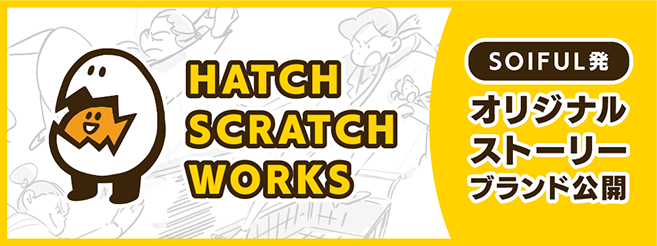SOIFUL対談企画
第2回:鳥海ひかり×栗田唯「感情を描く技術とストーリーの力」(中編)

中編では、ストーリーボードを「試作映画」と定義し、その哲学と本質に迫ります。脚本を映像に変換するために必要な「感受性」「表現力」「アイデア力」の3つの力、キャラクターの弱みを通じた心を動かすシーンの設計術、そして日米の文化的アプローチの違いについて深く語り合います。
/ Interview
中編では、ストーリーボードを「試作映画」と定義し、その哲学と本質に迫ります。脚本を映像に変換するために必要な「感受性」「表現力」「アイデア力」の3つの力、キャラクターの弱みを通じた心を動かすシーンの設計術、そして日米の文化的アプローチの違いについて深く語り合います。
※注記:本インタビューの内容は鳥海ひかり氏個人の見解であり、所属スタジオに関するものではありません。
ストーリーボードの哲学と本質
ストーリーボードとは「試作映画」である
栗田唯(以下、ユイ)ストーリーボードの定義と役割って言うと少し固い言い方になるけど、ひかりちゃんはストーリーアーティストってどういうところに役立ってると思う?
鳥海ひかり(以下、ひかり)ストーリーボードって何ですか?って聞かれた時には、脚本を絵に起こしてビジュアル化する紙芝居みたいな段階です、って答えてます。
何でそれが大事なのかと言うと、その真髄は、描いた絵そのものっていうよりは、それを使ってミニ映画が一本作れるところだと思ってます。その紙芝居(ストーリーボード)を、このコマ何秒、このコマ何秒っていう感じで伸ばしていけば映像化できるんですよね。そうすると、映画(映像)ってタイムラインがあって初めて成立するものなので、その簡易バージョンが作れる。
映画を全部作らずに「試作」を作れるっていうのが、一番大事なストーリーボードの強みなんじゃないかなと。
なぜそれが大事かっていうと、90分の映画があったら90分作ってみてそれを座って観て、初めて面白いか面白くないかって言えるじゃないですか。映画っていう媒体に一番低コストでアプローチできるプロセスなので、それが大事なんじゃないかなって思ってますね。
ユイすごく分かりやすい!本当その通りだなと思って。紙芝居だけでは成立しなくて、映像になってやっとミニ映画ができて、それを試作として感想を言い合えるわけだよね。
ひかりこの仕事をしてて必要性を感じるのは、テンポなんですよね。仕事を始めた時はまだ絵を描くのに忙しくて、1枚1枚の絵を仕上げるのに精一杯で、それがどう生きてくるのかってことにあんまり目を向けられてなかったんですけど。最近思うのは、そもそもちゃんと必要な情報を伝えてるのは前提として、それを映像に起こした時に、テンポとか流れっていうのがあるじゃないですか。それを見ることが一番大事な工程なのかなって思ってて。
絵は別に、ちゃんと感情とかアクションを説明できてれば最低限それでもいいんです、なぜならアニメーションでプラスしてもらえるから。そこを置いておいて、一番大事なのが、このシーン長すぎないかな、ここスローダウンしちゃってるなみたいな感じをパパッと見れること。ストーリーボードがあって、かつそこにスクラッチの音声や声優さんが入ってて、効果音とか音楽がついた状態で見た時に、これ見ててテンポいいかどうかっていうのを分析できることの方が、ストーリーボードの本当の価値っていう意味があるのかなって最近思ってます。
絵やストーリーボードのクオリティが一定レベルあるのは前提なんですけど、それをどう使うかっていう意味だと、テンポとか映画としてのタイムライン上での調整を早い段階からできるっていうのは、監督さんにとってはそこが一番大事なんじゃないかなって思うんですね。
反復制作プロセスによる品質向上
ユイストーリーボードを説明してるとよく言われるんだけど、せっかく描いたものをまた消すって、無駄なように思われてしまうことがあって。それが無駄じゃないって、どう伝えたらいいかな?
特に大手スタジオではスクリーニングを5回6回とかどんどん描き直して、描き直すだけクオリティが上がるっていうふうにやってるけど、描き直していく過程で、どうやってクオリティが上がってることを実感する?
ひかり(ハリウッドにおける一般的なフローとして)まずストーリーボードを描いて、これで一回編集しましょうってエディターの人に渡すんですが。ユイさん分かると思うけど、エディターの人って自分の部屋があって、試写室みたいな感じのでっかい部屋なんですよ。
そして、エディターさんが準備できたら、そこに監督さんたちが入ってきてその場でプロジェクターで見るんですよね。その見ているものは最初のアニマティックなので、出来立てのストーリーボードに仮の声優さんが入って、音楽も仮のものがついてる、っていう状態を見るわけです。
それを監督さんが見て、「ここちょっと中だるみしてるな」と感じたら編集でそこをもっと早回ししたり、またはそのアイデア自体が上手くいってないと思ったら、このギャグカットしましょうとか。ここのシーン良かったけどもうちょっと感情的にしないと、次のシーンで2人が再会した時になんでこんなに思いが高まってるのか分かんないから、ここでもうちょっと説明しとかないとって、そういった修正箇所がたくさん出てくるんですよね。
ユイはいはい。わかるわかる。
ひかりそれをちゃんとアクションアイテムにして、これは編集で音楽とか調整してどうにかなる話、これはそもそも台詞から書き直さないといけないからライターから始めないといけない、これは台詞は同じだけどアクティングを直さなくちゃいけない、っていうノートが出るんですよ。
これらのアクションアイテムをやっつけて、スクリーニングの1サイクルが終わるわけです。
そして2サイクル目として、さっきの修正箇所を直して、もう一回映画が一本仕上がったら、それをもう一回観て前回問題になっていた、例えば途中で話が中だるみしちゃってるところだとか、最後のクライマックスのシーンがいまいちハマってないみたいな、そういう修正箇所がちゃんと改善されてるかっていうのを確認していくんですよね。これを5回、6回と繰り返して。
ユイストーリーボードと同時にセリフもバンバン書き換わるわけやんか、(ハリウッドは)そこの時間の使い方が違うなと思いながら今聞いてました。
※スクリーニング:ストーリーボードに仮の音声や音楽を付けて映像化したものを監督やチームで鑑賞し、作品の流れやテンポを確認・評価する上映会。
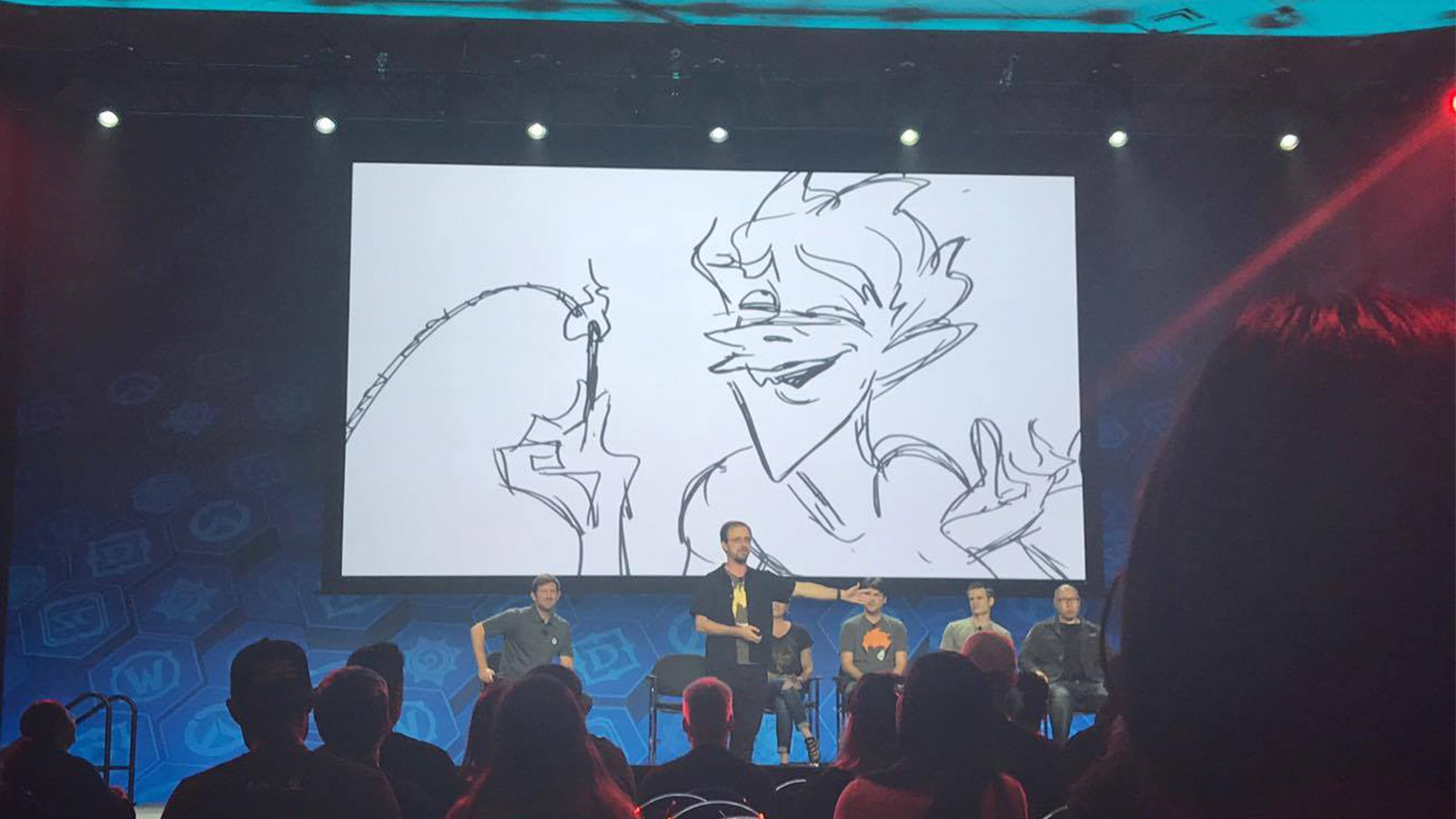
BlizzConで栗田唯のストーリーボードが紹介された様子
脚本を映像に変換する3つの力
ストーリーボード制作に必要な3つのソフトスキル
ユイじゃあちょっと話変えるけど、ひかりちゃんは脚本を受け取ってからどういう順番でストーリーボードを描き始めるの?
ひかり脚本からストーリーボードに変換するにあたってなんですけど、アサインメントをもらってから仕上げるまでに必要なソフトスキルを3つに分けられるなって思ってて。それは「感受性」と「表現力」、「アイデア力」っていう3つです。
まず最初の「感受性」っていうのは、脚本から監督さんが何を言いたいのか、どういうシーンにしたいのかを読み取る力が必要で。私、中高の頃に読書がすごい好きで、一時期は3日に1冊くらいのペースで1年に100冊読んでいたので、その辺りが活きているかもしれませんね。
読書を通して、文字でもらった情報を頭の中で映像化する習慣は割とありました。それが日本語から英語になった時は難しくなりましたけど、やっぱり基本のスキルとして大事だなと思いますね。
というのも、私たちって監督さんの映画を映像化するために仕事してるんで、監督さんがやりたいことと違うことをやっちゃうと、それはハズレになっちゃうじゃないですか。なので最初の段階でできるだけ、この人はきっとこういう映像にしたいんだろうな、こういう映画にしたいんだろうなっていうのを、脚本から読み取る感受性は必要だなって思ってます。
そこから次の段階で必要なのが「表現力」です。表現力っていうのは画力とも言い換えられるんですけど、自分の感受性で受け取った、この人はこういう映画を作りたいんだなっていう情報を、ちゃんと絵に起こさないといけないじゃないですか。わかってても、絵が下手だったり、演出が下手で、それが再現できてないと意味がないので。
私たちの仕事は、まだ文字でしかなかった情報を映像化する、絵に起こすのがメインなので、その意味で画力はあればあるだけ良いって思うんですよ。自分が使える演出力だったり、構図だったり、表情のレパートリーが多ければ多いほど、自分が使える技が多くなるので、そこの豊かさっていうのもボードを描いている最中は大事なんですよね。
その2つが脚本を監督さんの思い通りに忠実に描くために必要なスキルなんですけど、それにプラスアルファで大事なのが「アイデア力」だと思ってて。量ですよね、どれだけアイデアを出せるか。
脚本をそのまま忠実に絵に起こすっていうよりも、今脚本はこうなんだけど、そこにもうちょっとギャグ足してとか、ビジュアル的に面白くなるようにアクティング足してとか、そういうのって言われることもあるし、言われなくても暗黙の了解で、それくらい良くしてくるのが当然だよねっていう感じなんです。脚本の状態よりもプラスアルファで良いものにしないといけない。そこに持っていくために、やっぱりアイデアの引き出しをどれだけ持ってるかっていうのは、あればあるほど有利だなって思ってます。
引き出しを増やすための実践法
ユイ感受性を高めるためには本をいっぱい読む、表現力を高めるには絵をいっぱい描く、とイメージできるんだけど、アイデア力を高めるには何をすればいいのかな?
ひかり映画を観るのは、本を読むのと絵を描くのと同じくらい大事だと思うんですけど、私の場合は映画とかNetflixをソファにゆっくり座って観るのがすごい苦手で…
逆に、ドキュメンタリーとか、あんまり感情を入れなくていい動画だと普通に見れるんです。動物のサバイバルみたいなやつも大好き。ストーリー性が出てくるとめっちゃ疲れちゃうんですよね。
ユイでも面白いよね、そういう(ストーリー性のある映画をつくる)仕事してるわけやんか。
ひかり私気づいたのは、映画を「観る」のが好きじゃなくて「つくる」方が好きなんですよ。
ユイくぅ~、カッコイイですね!
ひかり今めっちゃカッコつけて言いましたけど、たぶん将来これがネックになると思ってて。今まで私のフィルムレパートリーっていうのは、母がめっちゃ洋画見るの好きで、VHSの時代から全部録画してラベルつけて、DVDになったらアルファベット順に整理するタイプの人だったんです。それを毎日同じものをずっと見てたおかげで、90年代から2000年代の洋画は多少詳しくなってたんです。
ユイアイデア力を高めるには、映画を観るのも方法の一つなんだね?
ひかりそうですね、アイデア力はどれだけ引き出しがあるかによってくると思います。それが具体的に役立つシーンとしては、ストーリージャムみたいな会議中に、例えば「こういうことしたら面白くない?」みたいな感じでギャグを言ったりするじゃないですか。
私はあんまり面白いこと言えない人間なんで、いちいちすごい考えちゃうんですけど。面白いことをさらっと言える人たちの「面白いこと」って、新しいアイデアも必要なんですけど、ある程度みんなが「わかる、わかる!」みたいな感じの共感性も必要で。「すでに見たことある」っていうのと「新しい」を、ちょっと混ぜないといけないんですよ。
「見たことある」っていうのは、みんなが見たことあるものが共通認識のレベルになっているところを、どれだけ知っているかになるので。そんな分析をしてる時点で、私は多分面白いことは考えられないんですけど(笑)。
ユイまさに俺、Blizzardでそれにぶち当たってたから、ひかりちゃんの言ってることが本当よく分かって、それがめちゃくちゃストレスやった。言いたいことがあるのに、英語力(の不足)もあるし、みんなが知ってる前提のもの、当たり前のものも知らないし。
僕ら日本人だったらサザエさんとかドラえもんとか、アンパンマン知ってるけど、そんな話を外国人にしてもピンと来ないのと一緒で、(現地で言う)アンパンマンやドラえもんみたいな話されても、「分かんない…」ってなっちゃって。そんなこと考えてるうちにもう違う話になってたりで、そのスピード感についていけなかったなってのはすごく覚えてる。
ひかりそこですよね。私がアイデア力って言った時に、自分が一番つまずきやすいのがコメディ系なんで、コメディはアイデアが本当にたくさんないと太刀打ちできないなと思うんですけど。
ユイその会議中に、もちろん使えないって分かった上で、あえて面白いこと言う人もいる?
ひかりいるいるいる!憎たらしい私はそれが。捨てるほどのアイデアがあるんだったら私にくれみたいな(笑)。
ユイははは(笑)。あれに俺憧れるね、カッコイイし、まさにジャムしてるよね、その場の雰囲気をぶん回してるというか。その場が沸くもんね。会議が明るくなるし、いい作品作るためには、みんなで睨みっこしながらやることじゃないもんね。今の話を聞いて、あらためてその場で面白いこと言うやつがいるのが重要だなって思いました。


鳥海ひかりさんが手がけた『ONI ~ 神々山のおなり』プロモーション用画像の一部


鳥海ひかりさんが手がけた『ONI ~ 神々山のおなり』プロモーション用画像の一部
心を動かすシーンの設計術
キャラクターの弱みを通じた感情表現
ユイ他の話も聞いてみていいですか。観客の心を動かすシーンの作り方と、その日米のアプローチの違いについて。こんな質問されても困っちゃうかもしれないけど、心を動かすにはどうしたらいいと思う?
ひかりそうですね。私的にこの質問には、真っ向から答えずに答えようかと思うんですけど。私がストーリーアーティストとしてもらって、これは美味しいぞっていうシーンは、そのキャラクターの弱みが見えるシーンなんですよ。
それの何が美味しいかっていうと、キャラクターの弱みって、そのキャラクターが一番大事にしてるものに直結してることが多いんです。そういうのが見えるシーンをいただくと、美味しいですね。よだれ垂らしてやってます(笑)。
音楽を設計資料として活用する手法
ひかりそういうシーンをやるときに、さっきもちょろっと言ったんですけど、私、音楽っていうかサントラを聴くのが結構好きで。感情って設定資料とかが存在しないのでつかみづらいんですけど、音楽は設定資料になるなって思うんです。特に、映画のサントラだと、キャラクターの感情の起伏に合わせて展開が進むじゃないですか。
だから、同じような展開をたどったシーンなら、同じような感情が流れてるわけで、そこに音楽って結構忠実に沿ってつくってあるので、こういう展開にすればいいんだなって見えてくるんですよ。
ユイでもそれって、今やってるシークエンスに合うサントラを探すの大変じゃない?どうやるの?
ひかりそういう意味で、映画を見てると役に立つかもしれないですね。
ユイこのシーンに似てる映画を思い出して、音楽だけ聞きに行く感じ?
ひかり私、音楽はからきしなんですけど、サントラ最初の3秒当ては得意なんです。イントロドンみたいに、タタタタタタ…♪、「はいっ、ザ・スピリット!」みたいな感じで当てられるくらいサントラ大好きで、好きになると何万回も聞きます。
映画はそんな好きじゃないけどサントラだけ好き、みたいなのもあるので。そういうレパートリーの中から、このイメージはこの曲って選ぶ感じです。サントラじゃなくてアニソンでも全然いいんですけど。
ユイあるんだ、自分の中にストックっていうか、棚がすごくあるから、このシーンに合うやつもすぐ選べるわけね。なるほど。音楽からインスピレーションをもらって心を動かすシーンを作れるってことか。
ひかりもっともらしく言うとしたら、観客の心を動かすにはキャラクターの心が動いてないといけないじゃないですか。そのキャラクターの心が動いているのを明確に参考にできるのは音楽なんですよ、音楽は展開があるので。
ユイすごいなぁ。でもね、ひかりちゃん、凡人を代表して言うと、やっぱりこれって天才の話なんですよ、僕からすると。見えない景色な気がするんだよね。天才がまた言ってるなってちょっと思っちゃって。すごくこう、つかめたようなつかめないような感じ。
実は恥ずかしい話、真似したことあって、僕も音楽から聞いてみようって。ひかりちゃんだったらこうやるんだろうなって聞いてたんだけど、ただ音楽を楽しんだ人で終わっちゃって(笑)、その映像やらなんやらがあんまり見えないっていうか。DICE(堤大介監督、以下DICE)さんも同じようにやってるって言ってたやんか、確か。
ひかりDICEさんも音楽って言ってましたね。
ユイそう、だからなおさらそう思うんだけど、なんていうのかな。天才って言葉でまとめたくないんだけど、でもそう感じざるを得ないぐらい見えない景色だなって思っちゃったんだよね。ひかりちゃん、これ言われてどう思う?
ひかりでも、そういう感覚が人によって本当に違うんだなっていうのを最近思ってたので。私のメソッドはユイさんには合わないんだろうし、ユイさんのコメディみたいなのを私はどう頑張っても真似できないので。
ユイまあその、なんていうのかな、適材適所って言葉は硬いけど、でもそういうことだよね。ストーリーアーティストって一括りにストーリーアーティストだけど、このシーンならこの人って振り分けられることあるやんか。コメディならこいつ、ドラマならひかりちゃんに任せようとか。どこで輝くかっていうのはやっぱりあるなって思う。今のひかりちゃんが言うそのつくり方は、ドラマ向きの考え方な感じだなって聞いてて思った。
ひかりそうですね、感情を動かすっていうか。それを強みとしてやらせてもらって、今のところ上手くいってるのでいいんですけど、それ一辺倒だとさすがによくないなと思ってて。最近はもうちょっと広げないといけないなと。
ユイオールマイティにやる人っている?コメディでもアクションでもドラマでも全部超上手いみたいな人ばっかり?
ひかりいます!でもみんな本当に人によりますね。本当に全部できる人もいるんですけど。ベテランかどうかは関係ないです、本当に。私より年下でもめちゃくちゃ上手い人いるし、同年代でも、脳みその構造が違うんだなっていう人がいるので。ヨーヘイさん(小池洋平氏)もおっしゃってましたけど、そういう人たちに囲まれてるのは十分に面白いですね。
ユイやっぱすごい世界だな。そうだよね。いやー憧れるな。

鳥海ひかりさんのオリジナルイラスト
日米の文化的アプローチの違い
四季感謝と暗示的表現の日本文化
ユイ次に、日米のアプローチの違いって、どう言えるかな?
ひかりちょっと話広げるんですけど、文化でも違うなと思ってて。私ここカリフォルニアに住んでてしょっちゅうむかついてるのは、四季に対する感謝みたいなものが全然ないんですよ、日本の比じゃない。
ユイめっちゃわかる。
ひかりカリフォルニアでちゃんと桜も咲くんですけど、並木道とかもちゃんと桜咲いてるんですよ。なのに誰も写真も撮らないし、誰もお花見で、その下でご飯を食べようともしない。私はキレ散らかして、こんなに頑張って咲いてるのに、日本だったらニュースになるんだよって。日本だったら桜前線っていうニュースなんだよって。咲く前からいつ咲くかっていう話をしてるんだよって言うんですけど、(こっちの人は)「あ、咲いてるね」みたいな。
あと最近平安時代の文化とかちょっと勉強してて思うのが、和歌とかでもそうなんですけど、いかに自分が寂しいですっていう単語を言わずに、あなたのことを思ってますよみたいなことを、葉っぱの色だとか、川の流れ方とかで、まだるっこしく説明しようとするじゃないですか。
ユイ言わずして言っていく感じだね。
ひかりそこに神経を注いでることが、今のエンタメの表現方法にも確かにつながってる気がしますね。
極端に言えば、アメリカではキャラクターを見せて、キャラクターでいかに感情を表現するかにすごくフォーカスが当たってて、日本の場合は、いかにキャラクターを見せずに感情を伝えるかっていう。
ユイそれは本当にそうだね。すごくいい。
関連記事
後編はこちら
後編では、ヴィラン(悪役)の魅力から始まり、プロアーティストとしての体調管理、そして創作の喜びまで幅広いテーマを語り合います。なぜ悪役は魅力的なのか、長期的なキャリアを築くための健康管理、絵を描く際の「ゾーン」体験について深く掘り下げます。
前編はこちら
前編では、鳥海ひかり氏のキャリアの軌跡について語りました。アニメーターからストーリーアーティストへの転身、Pixar時代からGlen Keane Studios、TONKO HOUSE『ONI』での協働、そしてDisneyへの道のりについて。
- Yui Kurita / Interview
- Hiroyuki Tsuiki / Editing